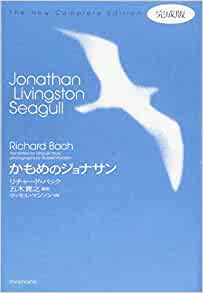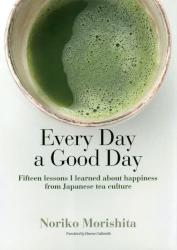推薦図書紹介
「自身の頭で考え、『世間の空気』に流されず、常に醒めた冷静な目で、自身の置かれた状況や自身が属する社会や国を見定める」には、どうしたら良いか。その具体例が歴史小説家の著者の視点で書かれたエッセイ。
- 13P
「ちなみに、”夢もなく、怖れもなく”とは、拙著『ルネサンスの女たち』(中央公論社)の第一部、イザベラ・デステの副題に使ったもので、彼女はそれを、生涯のモットーにしていた。(中略)”夢もなく、怖れもなく”といっても、夢と怖れとも完全に無関係な生き方を言っているのではない。もしそれをできる人がいるとすれば、まずもってその人は、感受性に完全に欠けている非人間であろう。だから、音楽の練習に使うメトロノームに譬えれば、左右に振幅を繰り返す針がだんだんと振幅の度を少なくしていき、最後にピタリと中央で止まるのに似ている。振幅は夢と怖れであり、中央で止まった時にはじめて、夢もなく怖れもなくの心境に達するのだ。」
江戸時代初期に起こった日本史上、最大規模の一揆である島原の乱を描いた小説。生存が不可能なほど領民から年貢を取り立てた松倉家に対し、無抵抗を貫いてきた旧キリシタンが、どのように蜂起に至ったかが描かれる。
- 316P
「背後に雲仙獄をひかえる南目の住民は、はるか遠い昔の噴火の記憶を有していた。人々の心の奥底には、人間の意志や力などを一呑みにする凶暴な火の記憶が常に潜んでいた。キリシタン宗がとりわけ南目で易々と受け入れられ、しかも根強く残り続けた背景には、言葉によって歴史が記述されるはるか以前の恐怖の記憶が手伝っていた。(中略)
秀吉も、あるいは家康も、人民の思想統制としてのキリシタン禁令を意図したが、こと南目におけるキリシトの言葉は、単なる思想や知識以前の、そこに常にある自然の脅威を背景に、現実のこととして受け取られた。」
1949年に発刊されたディストピア小説だが、今、まさに、本著の内容が起こっている。人が生きる上で、何が最も許容し難いものか、本来、人間は何に対して抵抗しなければならないかを理解するために重要な著書。
- 82P
「分かるだろう。ニュースピークの目的は挙げて思考の範囲を狭めることにあるんだ。最終的には<思考犯罪>が文字通り不可能になるはずだ。何しろ思考を表現することばがなくなるわけだから。」
1970年に発表された本著は、世界で4000万部以上のベストセラーとなった。2013年、最終章Part Fourが加えられた「完全版」である本著が刊行される。なぜ著者が、1970年時点で執筆していたPart Fourを、今になって加えたのか、現在を知る私たちは理解できる。
- 11P(完全版への序文)
「タイプの文字は消えかけていたが、言葉はわたしの精神のこだまであるように思われた。正確には、かつてのわたしの精神のこだま。これはわたしが書いたのではない、あいつが書いたのだ。あの時の、あいつが。
原稿を読み終わった時、わたしはあいつの警告と希望の声を充分に聴いたと思った。
『おれが何をしたかくらい、分かってるさ!』とあいつは言った。『あんたのいる二十一世紀は、権威と儀式に取り囲まれてさ、革紐で自由を扼殺しようとしている。あんたの世界は安全にはなるかもしれないけど、自由にはけっしてならない。わかるかい?』そして、最後にこう言った。『おれの役割は終わった。次は、あんたの番だよ』」
18世紀イギリスの外交官・政治家である著者が、息子へ向けた「良く生きるため」に必要な指針を記した書簡集。可能であれば十代のうちに本著を読み、自身で「すぐに実践出来そうな指摘、難しそうな指摘」等々、理解しながら生活に活かせば、人生が変わる。
- 41P
君も、良心や名誉に傷をつけることなく、社会のなかで立派にやっていきたかったら、嘘をついたりごまかしたりすることなく、潔く生きるといい。このことは、命ある限り頭にたたき込んでおきなさい。そうすることが人間としての義務であり、自分の利益でもあるのだよ。
著者の生家は、代々、法隆寺に仕え、当人は「最後の宮大工棟梁」と言われた。著者が宮大工として経験から得たものの見方に加え、飛鳥時代から継承される法隆寺大工の口伝は、本当の知恵とは何かを読者に気づかせてくれる。
- 18P
私は今年で八十五歳になりますが、これまで民家は一軒も造りませんでした。自分の家もよそさんに造ってもらいましたのや。民家は造ると、どうしてもいくらで何日までに上げねばならないと考えますし、儲けということを考えな、やっていけませんやろ。私はおじいさんが師匠でしたが、絶対に民家を造ってはならん、ときつくいわれていました。
言葉が悪い言い方ですが、儲け仕事に走りましたら心が汚れるというようなことでした。そのために私らは田畑を持っておりました。仕事がないときは田畑をやって、自分と家族の食いぶちをつくれということだったんでっしゃろな。
学生時代に「お茶」を習い始め、二十五年経った現在、著者が就職や失恋、父親との死別など経験しながら、いつもそばにあった「お茶」が、ものの感じ方、見方、五感を豊かに鋭くしてくれていたことに気づく。その経験をまとめたエッセイ。
- 28P
パラパラパラパラ・・・・・・
豆が当たるような音で、大粒の雨がヤツデの葉を打っている。
ポツポツポツポツ・・・・・・
テントをつつくような音をさせて、今を盛りの紫陽花の葉や、丸く大きくなった山茱萸の葉っぱたちが、元気に雨をはね返している。熱帯雨林を感じさせる雨だった。
『梅雨の雨だわね』
先生が、誰にいうともなくつぶやいた。
そのとき、気づいた。
(そういえば、秋雨の音はちがう・・・・・・)
十一月の雨は、しおしおと淋しげに土にしみ込んでいく。同じ雨なのに、なぜだろう?
(あ!葉っぱが枯れてしまったからなんだ・・・・・・。六月の雨音は、若い葉が雨をはね返す音なんだ!雨の音って、葉っぱの若さの音なんだ!)
1976年に著された社会科学的な書籍だが、本著の理論モデルを利用すれば、戦後から現在に至るまで、日本に起こった経済破綻やテロリズムが、なぜ起こったのかを分析できるようになる。
- 29P
現在(いま)は現在(いま)という刹那的な認識に立つ限り、高度経済成長以前の時代、ましてや戦前の事情などはいまとはなんの脈略もない別世界である。時間的に過ぎ去った時代から教訓を引き出して科学的に分析しながら、それを今日に生かすという基本的な態度が要請されるにもかからわず、これがない。-歴史は常に現代史であるというクローチェの指摘を思い出してみるといい。現在(いま)の危機とはまさにこのような初歩的な認識不足の態度の中にこそ胚胎する。高度経済成長という『最も空想的な人間の夢想をも絶する』社会変動を体験したにもかかわらず、われわれ日本人の行動様式は、構造的にも戦前のそれと同型(isomorphic)である。現在にあっても過去にあっても、日本人は依然として社会状況を科学的に分析し、これを有効に制御するという能力に欠けている。これはまことに戦慄すべき事実である。
題名に憲法とあるが、現在の日本国憲法の護憲・改憲を論じるのではなく、そもそも今の日本人が、憲法を生かし機能させられる思想・知見を持ち合わせているのかを本著は問う。そのため本著は思想史、民主主義・資本主義史をおさらいしながら、戦後の現代日本史について論じ、問いに答える。
- 53P
憲法とは国民に向けて書かれたものではない。誰のために書かれたものかといえば、国家権力すべてを縛るために書かれたものです。司法、行政、立法・・・これらの権力に対する命令が、憲法に書かれている。
941年12月の真珠湾攻撃のおよそ半年前、政府の極秘プロジェクトとして総力戦研究所が立ち上がった。同研究所には30代の政治・経済・軍事等々の各エリートが集められ、日米開戦後、どのような戦争の経過になるかシミュレーションした。それはその後に起こる現実とほぼ同じ予想となる。このシミュレーションが活かされなかったのはなぜか。
- 122P
<窪田内閣>は連日閣議を開き、日米開戦について論じた。すでに各<大臣>はそれぞれの所管について基本的データを揃えていた。インドネシアの油田地帯を占領し石油を確保するまではいい。しかしフィリピン基地から出動した米東洋艦隊によって、南志那海または南太平洋において輸送船団が攻撃され船団は壊滅されるだろう。青国政府は直ちに外務省より再三アメリカ政府に抗議する。しかし、受け入れられないだろう。青国陸海軍の出動、米東洋艦隊を撃滅する。日米開戦だ。
旧帝国陸軍大本営参謀の瀬島龍三は、戦後、シベリア抑留された後、伊藤忠商事で日米間の次世代戦闘機取引に携わる。それを契機に、日米安保体制下で歴代の首相・大臣・官房長官クラスのブレーンの立場を確立する。しかし、その瀬島当人は、一貫した思想を持ち合わせていたのだろうか。瀬島龍三の生き方が、戦後日本の姿勢と相似を成して描かれる。
- 129P
ガダルカナル戦さなかの四十二年秋、瀬島龍三を対米作戦主任に抜擢したのは当の服部だった。以来瀬島は作戦課の中核として陸軍の作戦計画を主導してきた。田中耕二が当時を振り返って言う。
『瀬島さんが能力を発揮できたのは、開戦前から一緒だった服部さんの存在に負うところが大きかった。服部さんもまた、カミソリのように切れる瀬島さんのバックアップでその権威を高めてきた。二人は互いに高め合いながら作戦課を引っ張ってきた』
京都府の町議から国会議員、自民党幹事長まで上り詰めた野中広務は、町議時代から政敵を徹底的に追い詰める一方、社会的弱者を守り抜く政治姿勢をもつ。なぜ、野中が政界で権力を持つに至ったか、また日本のどのような国策の転換期にあって、野中は影響力を失うに至ったか。野中の政治家人生の盛衰を追うことで、日本の政治史の大枠を掴むことが出来る。
- 12P
野中ほどナゾと矛盾に満ちた政治家はいない。彼には親譲りの資産も学歴もない。そのうえ五十七歳という、会社員なら定年間近の年で代議士になりながら、驚くべきスピードで政界の頂点に駆け上がってきた。『影の総理』『政界の黒幕』と異名をとり、権謀術数のかぎりを尽くして政敵たちをうち倒してきた。(中略)
しかし、その一方で野中はまったく別の側面をもっている。彼のもとには政治に見捨てられた社会的弱者たちが次々と訪れた。(中略) ハンセン病の西日本訴訟原告団理事局長だった堅山勲が言う。
『野中さんには『悪代官』みたいなイメージがあるでしょう。あれば百八十度違うと私は思いますね。素晴らしい政治家です。細やかな気配りがあって人間として温かい。言葉の一つひとつに、傷ついた者をこれ以上、傷つけてはいけないという気持ちがにじみ出ています。今、私は野中さんのことを手放しで信頼できると言いますよ』
2000年代前半、「鈴木宗男事件」に連座し、当時、外務省・国際情報局主任分析官だった著者は、背任容疑で逮捕後、512日間勾留された。本著はその間の獄中ノートをまとめたもの。同事件に連座し逮捕された政財界の要人の中には、「内面から崩れてしまった」人間もいるなか、著者は崩れず国家権力と個人で闘争し続けた。著者の内面にあるものとは何か。
- 123P
情報の仕事は、結局、人間対人間の真剣勝負なので、日々緊張の連続です。情報の世界では信頼、友情が最高の価値で、この信頼、友情はそれぞれの情報機関員の公の立場を超えたところでも存在するからです。人間性の勝負であるこの世界には独特の魅力があります。また、情報機関は、いかなる対価を払っても、機関員を守ります。残念ながら日本の外務省には、国際スタンダードでの情報(インテリジェンス)文化が存在しないことが、私を巡る事件で明らかになりました。
1985年、著者は専門職員として外務省に入省し、1986年、イギリスの陸軍語学学校へ語学習得のため留学した。本著は、当時出会った古書事業を営む亡命チェコ人から、神学や思想、チェコ人の歴史や思考法を個人授業として受けた頃の著者の記憶をまとめたもの。「絶対に正しいこと」が「複数ある」と見る著者の視座は、この亡命チェコ人から習得した。
- 73P
『しかし、チェコ人にも強力な民族意識があると思うのですが』
『確かにあります。小民族は強力な民族意識を持たなくては生き残ることができない。ただし、チェコ人の民族意識は、スロバキア人やポーランド人の民族意識とは異なります。スロバキア人やポーランド人は、民族主義に命を差し出すことができる。これに対してチェコ人は、自らの民族感情に対しても懐疑的です。これはチェコ人が何も信じていないことと関係していると思います。チェコスロバキア政府の統計によれば、チェコ人の過半数が無神論者です』
『共産党政権の政策に沿う回答をしているのではないですか』
『ちがいます。実際に過半数が何も信じていないのです。神を信じないのと同時に共産主義も信じていない。民族主義には宗教的な要素があります。チェコ人は何も信じていないので、民族主義も信じることができないのです』
杉原千畝の「六千人の命のビザ」により、ヒトラーから逃れ、神戸へたどり着いたユダヤ系ポーランド人の少年から物語は始まる。個人では抗しきれない国家的な暴力に対し、東欧、シベリア鉄道、日本に至るにつれ、少年は国家や民族の生存を左右する重大情報=インテリジェンスの本質を習得する。日本語で書かれた数少ない本来の意味での「スパイ小説」。
- 45P
アンドレイは市場に全力で駆けていった。十二角形の売り場の十二番だけがすでに窓の扉を開けていた。
『これから列車に乗ってお母さんと遠くに行くことになったんです。おいしいベーグルを買いにいつか必ず戻ってくるよ』
漆黒の瞳の奥には常と変わらぬ慈愛に満ちた光が湛えられていた。
『アンドレイ、お母さんに伝えなさい。お前たちの針路は北だと。いいね、北の方角だよ。北極星を目指して進み、それから東へと向かうんだ。そうすればお前たちは必ず生き延びられる。両親を大切にするんだよアンドレイ』
その預言は、三百歳の老婆の叡智に満ちていた。
十二番の売り場もまた真北に面している。エステルというその名こそユダヤの民がかつて生んだもっとも偉大な女預言者の名だった。
者らは「インテリジェンス」をキーワードに、2006年から共著し、2012年からは1年に1度のペースで、世界情勢に関し対話を続ける。「危機」、「目を背け無視したいおぞましい現実」、「事前に想像不可能と思われる実際に起こる非常事態」の重大情報を、いかに捉え生き残りに活かせるか。当シリーズは時事問題を解きながら、その技法を読者に伝える。
- 150P
佐藤 いまの中国の強権的な政治体制と膨張主義が、日本をはじめとする東アジア、そして西側同盟を束ねてきたアメリカにとって、大きな脅威に映っていることは間違いありません。ただ、それはスターリン時代のソ連とは明らかに異なります。」
「手嶋 それだけに、かつてのソ連といまの中国を二重写しにして脅威を言い立てるだけでは、『二十一世紀の中国』といかに対峙していくべきか、的確な『解』を見つけることはできません。佐藤さんと本書を編んだ理由はこの一点にあると言っていいですね。
著者は、研究者として人民解放軍の分析を長年にわたり継続してきた。題名に「軍拡」とあるが、人民解放軍の軍事力の分析は、本著の終章のみで、政治・文化を含む中国現代史が議論の中心。今の中国を包括的に捉えられる。特に、現代の中国共産党の「生まれと育ち」を押さえた内容になっているため、同党がなぜ現状のような行動を取るのかが理解できる。
- 41P
中国を訪れる外国人観光客の多くは、北京の紫禁城や万里の長城などをみて、中国は偉大な文明を誇る国だと感嘆するに違いない。しかし、そうした巨大建造物は、実は極端なまでの富の偏在を象徴しており、その裏側では数十万、数百万の民衆が餓死するという凄惨な飢饉が高い頻度で繰り返し発生していた。飢餓への恐怖は、民衆の一部を略奪集団、すなわち匪賊へと変貌させ、中国全土で匪賊集団が自己の生存のために他の民衆を襲い、王朝に対して牙を剥いた。
そうした環境下で、民間社会は自治と自営の伝統を育み、人々は自分たちの知恵と才覚と腕力を以て自分たちの面倒をみていた。国家権力に依存せず、期待せず、場合によっては服従もしないという中国の民間社会に見出すことができる逞しさ、自立性、抜け目のなさは、永きに及んだ国家権力と民間社会との疎遠な関係によって育まれたものといえよう。
日本近現代史の研究者の著者が、高校生に明治初期から太平洋戦争までを講義する。著者は対話を通じて高校生らに「当時の日本、戦争を生きて」もらうことに成功している。国家は日本国民に対し、どのような戦争の正当化の論理を説いたか。本著を通じ「当時の日本で生きていたら、確かに自分も戦争を選んでいた」と実感するか、自身に問うべき。開戦と敗戦を日本国民が自分のもの、自らの責任のものにしなければ、「戦後」は終わらない。
- 265P
序章で、リンカーンの演説を説明したとき、ルソーの戦争論『戦争および戦争状態論』の話をしましたね。(中略) つまり、ある国の国民が相手国に対して、『あの国は我々の国に対して、我々の生存を脅かすことをしている』あるいは、『あの国は我々の国に対して、我々の過去の歴史を否定するようなことをしている』といった認識を強く抱くようになっていた場合、戦争が起こる傾向がある、と。
この点でいえば、満州事変前、東京帝国大学の学生の九割弱が、満蒙問題について武力行使に賛成だったという事実を思いだしてください。九割弱の人々が武力行使すべきだと考えていたということは、満蒙問題が、日本人自らの主権を脅かされた、あるいは自らの社会を成り立たせてきた基本原理に対する挑戦だ、と考える雰囲気が広がっていたことを意味していたのではないでしょうか。
著者は、貧困問題の活動を行うNPO法人の理事で、2009年から2012年の間、内閣府の参与を務めた。ホームレス支援に尽力していた著者が、政策決定に携わった経験を踏まえながら、「民主主義は面倒でうんざりする」システムでありつつ、主権者である日本国民は、そこから降りられないことを指摘する。著者は、東京大学大学院で政治思想史を研究していたことから、本著は平易な言葉で語られつつ、背後に政治史を踏まえた議論がなされている。
- 30P
状況を規定してしまうカリスマ性、反対意見を考慮しない大胆さ、『えいやっ』の即断即決力。これらが『強いリーダーシップ』の中身だと言いました。ここに示されている人格は、よく言えば『突破力がある』、悪く言えば『独善的』ということになるかと思います。(中略)
私が気になっているのは、なぜこのような人格が待望されるのか、それを待ち望む人たちの心理です。そしてそれがもたらす帰結です。(中略)
しかし他方、私はそれが、待ち望んでいる人たちに最終的に望ましい帰結をもたらすとは、どうしても思えないのです。
理由は簡単です。先に述べたように、日本では一億二千万の利害がひしめきあっています。そしてそれは、誰がヒーローになっても、基本的には増えもしなければ減りもしない。
1995年に地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教団の信者・元信者に対して、著者がインタビューを行ったノンフィクション。著者いわく、「あくまで実感として。肌の痛みとして。胸を打つ悲しみとして、地下鉄サリン事件とは我々にとって何だったのか」を知るための著書。同著者が被害者へインタビューした著書に『アンダーグラウンド』がある。
- 51P
論理的には簡単なんですよ。もし誰かを殺したとしても、その相手を引き上げれば、その人たちはこのまま生きているよりは幸福なんです。だからそのへん(の道筋)は理解できます。ただ輪廻転生を本当に見極める能力のない人がそんなことをやってはいけないと、私は思います。そういうことに関わってはいけないということですね。他人の死んだあとをしっかり見極めてそれを引き上げてあげたり、もしそういうことができるのであれば、あるいは(自分でも)やったかもしれないですよ。でもオウムの中で、そこまで行っているひとは一人もいないでしょう。
-でもあの五人はやったわけだ。
私ならやらない。その違いはあります。それだけの行いの責任をとる能力がまだ自分にはないからです。ですから怖くてとてもそんなことはできません。そこのところは曖昧にしちゃいけないと思います。他人の転生を見極められない人間には、他人の生命を奪ったりする資格はないです。
-麻原彰晃にはそれがあった?
そのときはあったと思っています。
禅宗の僧侶である著者は、「唯一絶対の真理とか、絶対の教えなどどうでもいい」と言う。本著は、「とにかく、生きにくいとか、生きがたいと思う」人に対して、それでも生きるにはどうしたら良いかという問題に応えた著書。著者こそが、自分が生きがたい感情を説明する言葉を求めて仏門に入った人間であった。
- 18P
そもそも『生きにくい』『生きがたい』という感情と『生きたくない』という感情は別です。『生きたくない』とは思わない人にも、『生きがたい』ということは起こりうるでしょう。
それに、生きがたい人が直ちに不幸かというと、必ずしもそうではありません。先々に何かをしたいと思える人、あるいは誰かのために生きようという人は、生きがたくても生きにくくても、『いまは大変かもしれないが・・・』と思いながら、なんとかやっていくものです。(中略)
一方、『生きたくない』というのは、自分の価値や、自分が存在する意味そのものが定かに見えなくなってしまっている状態でしょう。
いまの時代は、この『生きたくない』というのと、『生きがたい』というのが、同じことのようになっている気がします。つまり、何か具体的な困難があるから生きがたいというのではなく、むしろ生きたくないという感情が表にあらわれて、なお生きなければならない困難さのようなものがむき出しになっていることが、生きがたさにつながっている気がするのです。
第二次世界大戦中の1942年、ウイーンで精神科医だった著者はナチスにより強制収容所に収容された。初版は1947年に出版され、600万部を超える世界的ロングセラーとなる。収容所のなかで「生きていることにもうなんにも期待がもてない」人に対し、著者は、「生きることから降りられない」ことを伝えることに成功した。その気づき、意識とは何か。
- 54P
収容所暮らしが長い被収容者のこうした非情さは、いかに生きのびるかというぎりぎり最低限の関心事に役立たないことはいっさいどうでもいい、という感情のあらわれだ。被収容者は、生きしのぐこと以外をとてつもない贅沢とするしかなかった。あらゆる精神的な問題は影をひそめ、あらゆる高次の関心は引っ込んだ。文化の冬眠が収容所を支配した。
さもありなんというこうした現象にも、ふたつだけ例外があった。ひとつは政治への関心。これは理解できる。もうひとつは、意外なことに、宗教への関心だ。
ナチス支配下の強制収容所を生き延びた精神科医の著者は、1946年に「生きる意味と価値」について講演を行った。本著はその講演をまとめたもの。『夜と霧』が強制収容所で著者がみた現実そのものだとすると、本著はその体験を、思想や哲学に高めた書籍。
- 26P
あるとき、生きることに疲れた二人の人が、たまたま同時に、私の前に座っていました。それは男性と女性でした。二人は、声をそろえていいました、自分の人生には意味がない、『人生にもうなにも期待できないから』。二人のいうことはある意味では正しかったのです。けれれども、すぐに、二人のほうは期待するものがなにもなくても、二人を待っているものがあることがわかりました。その男性を待っていたのは、未完のままになっている学問上の著作です。その女性を待っていたのは、子どもです。(中略)
ここでまたおわかりいただけたでしょう。私たちが『生きる意味があるか』と問うのは、はじめから誤っているのです。つまり、私たちは、生きる意味を問うてはならないのです。人生こそが問いを出し私たちに問いを提起しているからです。私たちは問われている存在なのです。私たちは、人生がたえずそのときそのときに出す問い、『人生の問い』に答えなければならない、答えを出さなければならない存在なのです。
人は心が傷つくと、自分は弱くて駄目な人間と感じ易いが、著者はその傷そのものが、自分にとっていちばん大切なことは何かに気づかせる機会になると指摘する。心に傷を負っても自信を失ったりせず、「この傷が私なんだ、この傷の立ち直りが私なんだ」と、誇りを持つべきと著者はいう。精神科医の著者による心の傷を通じた自己成長のエッセイ。
- 15P
ただ、私にとってはその人の心の傷は、顔や学歴なんかより何倍も個性的で、そして場合によっては、生き生きと自己主張しているように見えることもあるのだ。だから、『ああ、こういう傷を持つあの人ね』と思い出すのは、少しもマイナスなこととは思えない。
傷は、自分にとって何よりも個性的なしるしであり、『私は繊細でやさしい』という証でもあるのだ。
原題は「The Road Less Traveled」。精神科医の著者は、自身の生き難さと向かい合うことを「旅行く人の少ない道」と表現し、心理的な治療と精神的な成長は、ほぼ同義だと説く。心理療法は独自に行うことも可能だが、精神科医との対話を通じた方が近道として利用でき、その一方で、原因を瞬時に解決する魔術的な方法でもないことを著者は指摘する。
- 65P
先に述べた例は、自らを患者と呼ぶ勇気のある人々が、心理治療の過程で何度も大きな形で経験することの、小型版である。集中的な心理治療の時期は、集中的に成長する時期であり、その間に患者は、人が一生のうちに経験する以上の変化を経験することがある。このような成長がほとばしり生じるには、それに見合うだけの『古い自分』が捨てられねばならない。
ナザレのイエスは、なぜ支配者であるローマ人のみならず、同胞のユダヤ人からも憎まれ迫害されたのか。その迫害された教えは、なぜ人類普遍の価値となったのか。師を見捨てた卑怯者の弟子たちは、なぜ死を怖れない殉教者に変わったのか。イエスを「銀貨三十枚」で売ったイスカリオテのユダは、なぜイエスの最も深い理解者だったか。著者は問う。
- 62P
聖書のなかにはあまたイエスと見棄てられたこれらの人間との物語が出てくる。形式は二つあって、一つはイエスが彼等の病気を奇蹟によって治されたという所謂『奇蹟物語』であり、もう一つは奇蹟を行うというよりは彼等のみじめな苦しみを分かちあわれた『慰めの物語』である。だが聖書のこの二種類の話のうち、『慰めの物語』のほうが『奇蹟物語』よりはるかにイエスの姿が生き生きと描かれ、その情況が眼に見えるようなのはなぜだろう。
著者の一人、佐藤氏は同志社大学大学院神学研究科を修了。「創世記」「使徒言行録」「ヨハネの黙示録」を通じ、神学的な思考法を解説する。小説家の中村うさぎ氏は、買い物依存症などあらゆる「世俗」を過去に体験した。平易な言葉で率直に聖書の言葉に疑問を投げる中村氏の問いは、神学的に最も深い問いを突いていることを、佐藤氏が明かす。
- 117P
中村 だから、奴隷の宗教としてのユダヤ教を読み替えたのがイエス・キリストで、そこに愛という概念を入れ、神の子が人間のために犠牲を払うという物語をつくったわけね。あのイエス・キリストがいなかったら、ここまでキリスト教が世界を席巻することはなかったと思うんですよ。
佐藤 ユダヤ教だけだったら、すごく狭い範囲の宗教で終わっていたでしょうね。
中村 私たちは新訳聖書を知った上でこの『創世記』を読んでるよね。ということは、この先、神が自分の息子であるイエスを犠牲として差し出すことも知りながら読むわけですよ。そうすると、神の過酷な仕打ちなんかも、ああ、これも愛の鞭なんだなと思って読めるんだけど、それを知らなかったら単なる過酷な物語で終わっちゃう。そう考えると、今も旧約を頑なに信じているユダヤ人って、不思議な人たちですよね。
実感とほぼ乖離の少ない小学校までの「算数」は、中学校から無味乾燥で感覚とほど遠いかにみえる「数学」に変わる。著者は数学の歴史にも詳しく、代数学や幾何学が、そもそも何のために作られたかにも精通する。中学や高校生が感じる数学への戸惑いは、数学史の巨人もまた経験したことを指摘しながら、数学と実感を結びつける解説を本著は行う。例えば「マイナス掛けるマイナスは、なぜプラスか」が体感として分かる。
- 17P
そこで困ったのが『負の掛け算の導入』だった。『規則だから覚えましょう』的な押しつけの教材ではなく、『なるほどそうか』と自然に掛け算の法則が飲み込めてしまうような、そういう教材を提供したかったからだ。(中略)
しれは、こどもたちに先ほどのように『正反対の言葉』を列挙させた時のことだった。その中で、『賛成と反対』という言葉を挙げたこどもがいた。その子は、この例を挙げたあと、『反対の反対は賛成なのだ』と赤塚不二夫のマンガ『天才バカボン』のせりふを付け加えて笑った。(中略)
『ある意見に反対する』というのを『マイナス』と捉えるなら、『反対の反対は賛成なのだ』というせりふは、まさに『マイナス掛けるマイナスはプラス』ということを意味している。気づいてみれば簡単なことなのだが、正負の数の掛け算を理解するためには、このように『方向算』というものを導入することが一番うまい手だったのだ。
本著は、地震、山火事などの頻度と規模、戦争の頻度と死者数、株価変動の大きさについて、実際のデータから統計分析する。著者はこれら全て、統計物理的な「べき乗」の法則に従うと指摘する。本著の仮説に従えば、長らく火事が起こらなかった山野からは大規模な山火事が起き、長らく平和を享受した世界の次に起こる戦争は、より多くの死者を生み出す。
- 34P
科学者でない人々は、バタフライ効果を、カオス理論という概念を端的に表したものととらえているようだ。しかしバタフライ効果としてよく知られている話は、残念ながら少々誤解を招くものである。風船の中の分子の運動がカオス的だったとしても、中で特に変わったことは起こらないはずだ。あなたは、中で嵐が巻き起こっている風船を見たことがあるだろうか?風船の中の蝶がいくら羽ばたいても、それが影響を及ぼすことはない。カオスだけでは、なぜ蝶が嵐を起こしうるのかを説明できないのだ。確かにカオスは、なぜ小さな原因が未来の詳細(各分子の位置)を変化させるのかを説明することはできる。しかし、なぜ小さな原因が最終的に大激変につながりうるのかを説明するには、何か別のものが必要なのだ。カオスは、単純な予測不可能性についてなら説明できるが、『激変性』について説明することはできない。
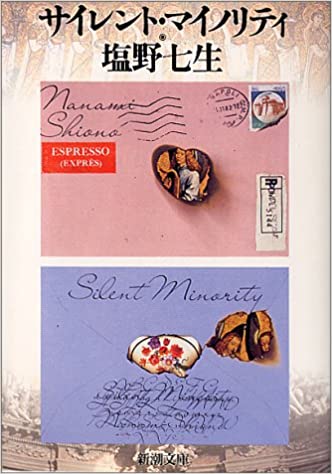

![一九八四年 [新訳版]](https://xn--u9jz52g5tqxu6a15f.com/wp-content/uploads/2021/03/mk3.jpg)